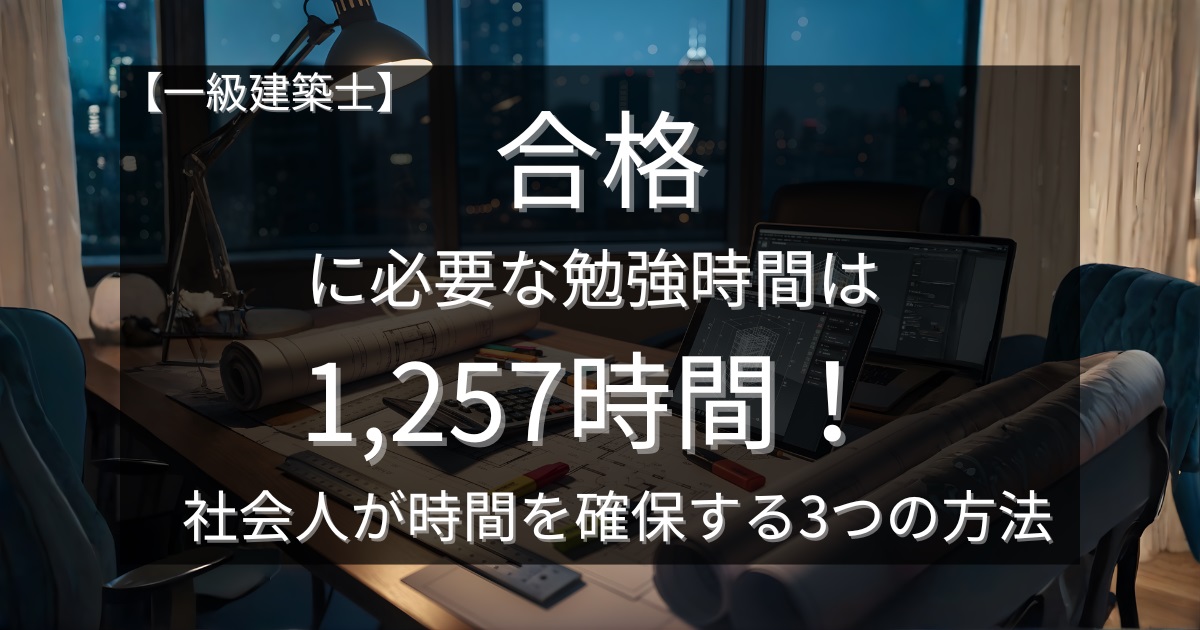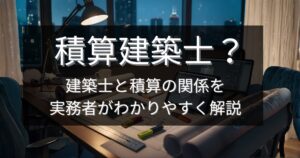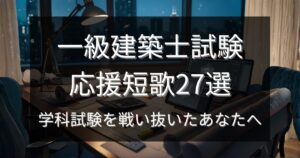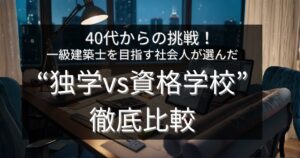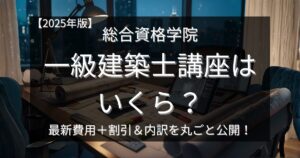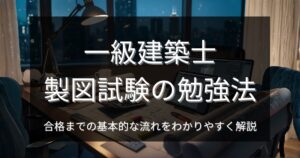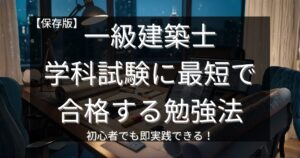一級建築士試験合格に必要な勉強時間は?
一級建築士の試験は建築系資格の中でも特に難易度が高いと言われています。
理由は以下の2点。
✅学科試験は5科目。試験範囲が非常に広い。
✅設計製図試験は実技形式。制限時間の6時間30分以内に手書き図面を完成させる。
学科・製図とも多くの知識が求められ、技術の幅も広いです。
必然的に学習時間も多くなります。
勉強時間の目安は1,000時間~1,500時間

一級建築士試験に合格するための勉強時間は、一般的には以下のように言われています。
📝学科試験:800~1,000時間程度
暗記だけでなく、理解力を問われる問題も多く出題されます。
特に「構造」や「法規」は、暗記だけでは対応しきれないため、時間をかけてじっくり理解していく必要があります。
📐設計製図試験:300~500時間程度
課題の理解・エスキス・記述・作図と多面的な能力が求められる試験です。
作図や記述は手書きのため、反復練習でスピードを上げることが合格へのカギになります。
学科と製図の勉強時間を合わせると、おおよそ1,100~1,500時間。
社会人の場合、この時間を捻出することはとても大変ですよね。
でも、安心してください。これはあくまで目安です。
大切なのは、
🧡どうやって勉強時間を確保するか
🧡限られた時間の中で自分に合った学習スタイルを見つけるか
ということです。
社会人が確保できる勉強時間は?
「一級建築士試験に合格するためには、1,000時間以上の学習時間が必要!?」
いきなり大きな数字が出てきましたね。
この数字だけを見ると、「本当にそんな勉強時間が取れるのか?」と感じるでしょう。
勉強時間を確保する方法といえば、
🚩早朝の時間を活用(朝型生活)
🚩通勤時間や昼休み、スキマ時間を有効活用
🚩家族と相談して、週末や連休にまとまった時間を確保
共通するのは、「日々の生活に無理なく組み込む」ことです。
小さな時間の積み重ねが、やがて1,000時間を超えていきます。
わたしは早朝の3時間を勉強時間にあてていました。
「まずは勉強を先に終わらせるて、残りの時間で仕事や家事をする」というスタイルです。
朝型生活を続けた結果、勉強時間は計1,257時間にもなりました。
私の勉強時間|1,257時間の内訳

私が受講した総合資格学院の教材に「合格Diary」という学習記録帳があります。
この「合格Diary」に毎日の勉強時間を書き込み、教務担当に提出します。
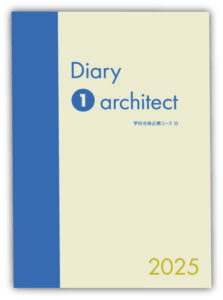
「合格Diary」に書いてあった勉強時間を合計すると1,257時間でした。
学科試験:10か月で1,025時間
学科試験の勉強時間はこんな感じ。
| 月 | 勉強時間 |
| 10月 | 89時間 |
| 11月 | 81時間 |
| 12月 | 83時間 |
| 1月 | 117時間 |
| 2月 | 87時間 |
| 3月 | 74時間 |
| 4月 | 57時間 |
| 5月 | 142時間 |
| 6月 | 122時間 |
| 7月 | 173時間 |
| 合計 | 1,025時間 |
😰5月以降は学科の試験日(7月末)が近づき、焦りやプレッシャーを感じた時期。
「とにかくやるしかない」と必死でした。
仕事が忙しいと、1日1時間だけの日や、全くできなかった日もありました。
それでも「少しずつでもやっておこう」と。
コツコツと勉強を続けた結果、10か月で勉強時間が1,000時間を超えていたのです。
▶ 学科の勉強法を知りたい方はこちら。
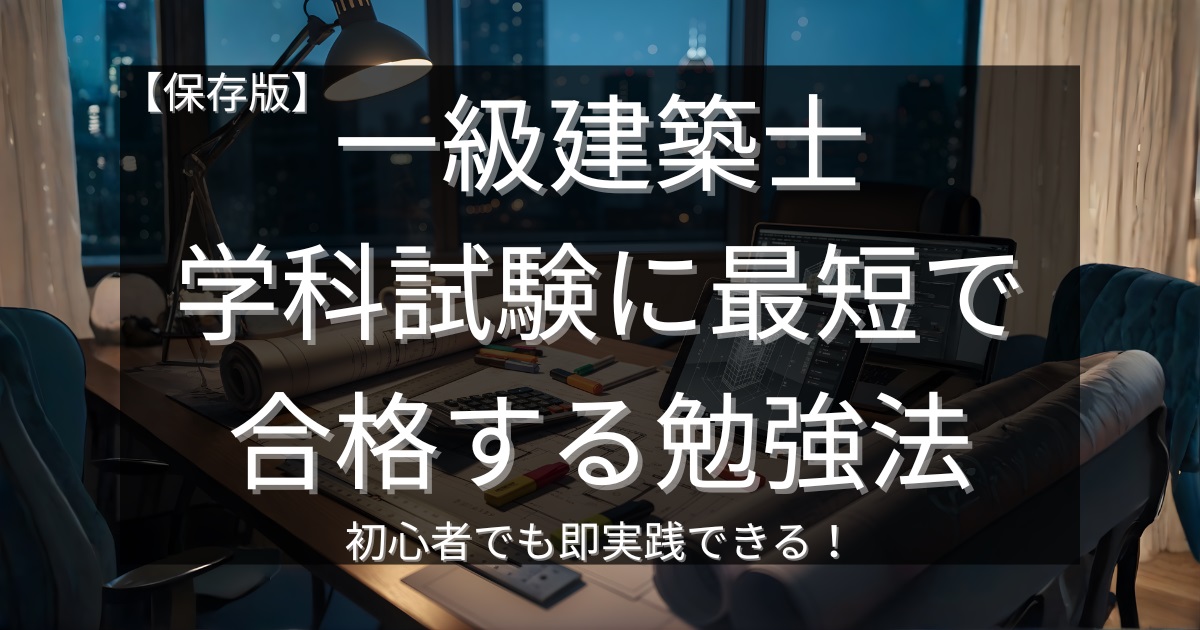
製図試験:約2.5か月で232時間
設計製図の勉強時間はこちら。
| 月 | 勉強時間 |
| 8月 | 36時間 |
| 9月 | 146時間 |
| 10月 | 50時間 |
| 合計 | 232時間 |
設計製図の対策は学科試験が終わった直後から取り組みました。
自己採点で合格圏内だったので、通知が来る前に試験対策を始めることに。
ただし、ここにきて困ったことが・・・。
設計製図の勉強方法がまったく分からないのです。
とにかく課題を繰り返し、図面を書きまくった結果、試験直前になんとか完成図が書けるようになり、本試験へ。
製図試験の勉強時間は232時間。
学科に比べると決して多くはありませんが、
短期間に集中して、追い込めたことが良かったと思います。
▶ 製図試験の勉強法はこちらの記事をご覧ください。
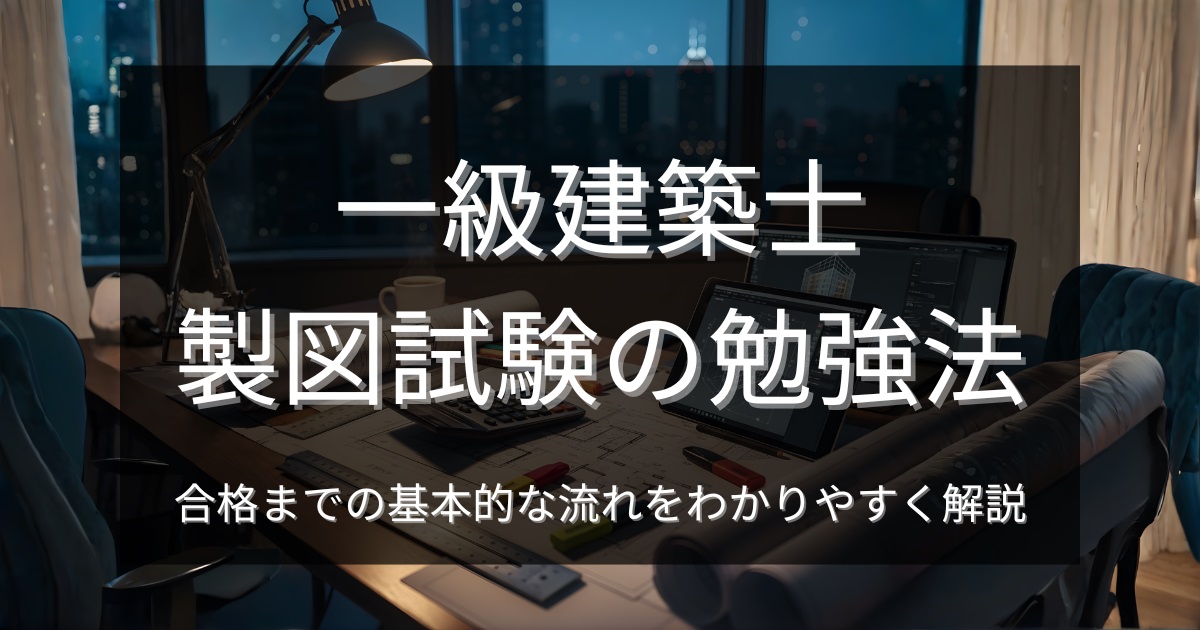
合計:1,257時間を勉強してわかったこと
一級建築士試験の合格に費やした勉強時間は、
💚学科試験:1,025時間
💚設計製図試験:232時間
合計1,257時間。
「よくこんなに勉強したなあ」と、自分でも驚きます。😲
”今日できること”をただ続けてきただけなんですけどね。
「少しだけでも進めておこう」と続けたことが、1,257時間につながったのだと思います。
少しずつでも、学んだことはちゃんと自分の力になっていきます。
勉強時間を確保できずに悩んでいるへ。
「まずは10分だけでもやってみる」ことをおすすめします。
その10分が、やがてあなたの1,257時間に変わるかもしれません。🌟✨😊
学習時間を確保できた3つの理由

働きながら一級建築士試験に合格するまでの勉強時間は合計1,257時間。
「どうやったらそんなに勉強時間を確保できるの?」と思いませんか。
理由① 朝型生活に切り替えた
みなさんは、いつ勉強していますか?
最初は夜型でした。
仕事を早めに切り上げて、夜22時頃から勉強をスタート。
でも、仕事で疲れた頭には、少々厳しかった。
暗記は頭に入らないし、問題集の進み具合も遅く、うまくいかない日が続きました。
「このままではダメだな」と考え、思い切って朝型にチェンジ!。
朝は頭がすっきりしていて、勉強にはぴったりの時間帯でした。
最初は早起きがつらかったですが、慣れてしまえば問題なし。
誰にも邪魔されない“自分だけの時間”として使えるので、落ち着いて取り組めました。
「朝やってしまえば、その日のノルマはクリア」😊
という安心感が大きかったです。
夜になって「今日の分、まだやってない…」😰と
焦ることがなくなり、気持ちに余裕を持って勉強を継続。
この「朝型生活」のおかげで勉強時間が安定。
毎日3~4時間の勉強時間を無理なく確保することができました。
理由② 合格Diaryを使って時間管理
総合資格学院の教材に「合格Diary(合格ダイアリー)」という記録用ノートがあります。
主な役割は、学習スケジュールの管理と勉強時間の記録。
毎日の学習時間と学習内容を合格Diaryに記録し、受講日に提出します。
講座を始めたころは「こんなもの書いて意味あるのかな?」と思っていました。
しかし、続けていくうちにその価値がわかってきました。
日々の勉強時間を“見える化”することで、
😓「今週はちょっと少なかったな…」
💪「模擬試験までには、ここまで終わらせておこう」
といった具体的な意識づけや目標管理にとても役立ったのです。
このブログを書く時にも合格Diaryはとても貴重な資料になっています。
改めて思う。
「あのとき記録しておいて本当に良かった」と。
▶ 総合資格学院の講座と費用はこちらの記事をご覧ください。
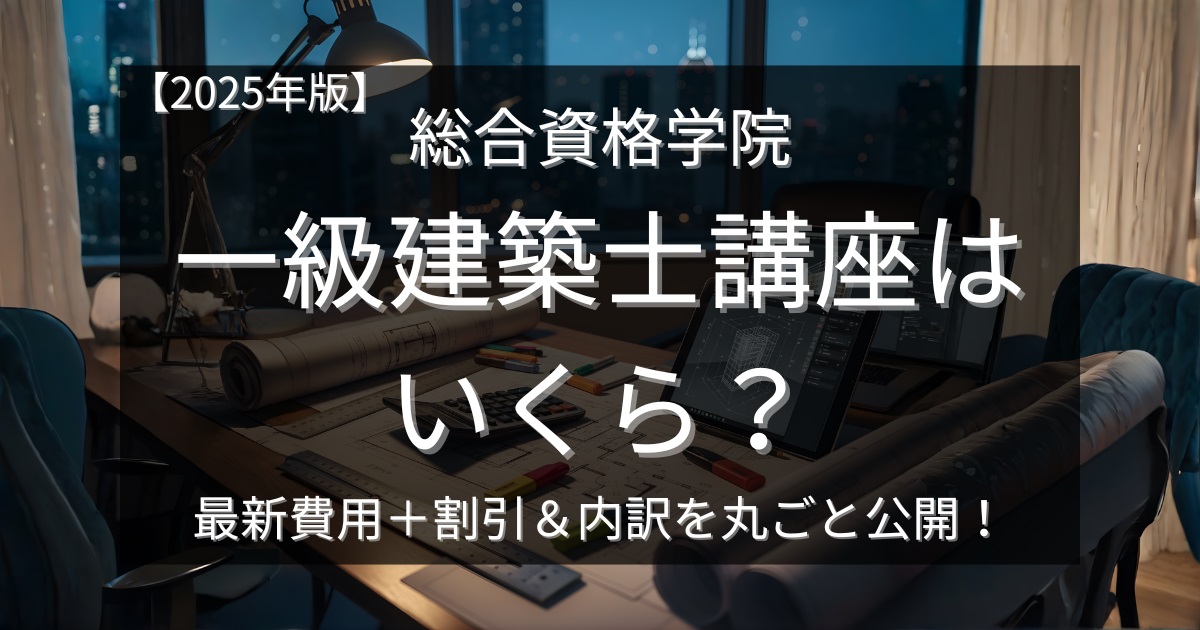
理由③ 数字で進捗を「見える化」
勉強を続けるうえで大きな助けになったのが、学習内容の「見える化」でした。
合格Diaryに記録した勉強時間や進捗状況を数字で目に見える形にしたことが、モチベーションの維持にしっかりとつながっていたと思います。
仕事が忙しくて予定通りに進まず焦った時は、合格Diaryを再確認。
「今日はできなかったけど、全体としては前に進んでいる」
と冷静に判断できるようになったのです。
こうした数値管理のおかげで、
😊日々の学習時間に一喜一憂しない
💪長期的な視点で自分をコントロールできる
こんな意識が自然と身につきました。
仕事や家事に追われて、「今日は何もできなかった…」と落ち込む日もありますよね。
でも、「今週はトータルで○○時間勉強できた」と分かれば自信と安心につながります。
この「数字の積み上げ」が、勉強を続けるうえで最大の支えになっていました。
補足1|やることが多すぎてペースを掴みにくかった1年目
学習時間の確保とは趣旨が異なる内容のため、興味のある方だけご覧ください。😄
一級建築士の勉強を始めた1年目。
「やることの多さ」に圧倒されました。
😄 講座の予習・復習
😅 小テスト
😖 提出課題
😨 過去問対策
😵 模擬試験
どれも重要なものばかり。
勉強時間がいくらあっても足りない!という感覚でした。
さらに私の場合、資格学校への入校が1月だったため、「途中からの参加」という状況。
入校時点で講座はすでに始まっていて、スタートダッシュから完全に出遅れていたのです。
遅れを取り戻すために、できる限りの工夫をしました。
✅ ビデオ講座をフル活用(倍速視聴で時短)
✅ 校舎へ通って自習室で予習・復習
✅ ポケット問題集を常に持ち歩き、スキマ時間を活用
やることが多くて学習リズムを掴むまではかなり時間がかかりました。
何を優先すべきか分からず、あれもこれも手を出しては、どれも中途半端に終わってしまう・・・。
そんなもどかしさと焦りの入り混じった日々でした。
特に初受験の場合、
🚩覚えること(インプット)が多い
🚩問題演習(アウトプット)の時間が足りない
これらは避けられません。
わたしの場合、1年目は残念ながら不合格でした。
ただし、続けていくうちに手応えはつかめた。
独学だったら、途中で挫折していたと思います。
試験範囲の全体像も把握できたし、自分に合った学習ペースも見えてきた。
「次は絶対に合格するぞ!」と心に誓い、迷わず2年目も受講を継続しました。
補足2|2年目はアウトプット中心で効率アップ
こちらの記事も学習時間の確保とは趣旨が異なる内容のため、興味のある方だけご覧ください。😄
1年目の不合格を経て迎えた2年目
9月上旬に不合格通知が届きました。
本音を言うと「もしかしたら受かっているかも?」と期待していましたが、やはりダメでした。
気持ちを切り替えて、9月中旬から始まる新しい講座を申し込み。
今回は最初から講座に参加できたので、心にも余裕があり、落ち着いて学習を進めることができました。
そして、何より大きかったのが、テキスト読み込み(インプット)から問題集(アウトプット)へ学習の軸を切り替えたこと。
勉強の時間配分はこんな感じ
1年目:テキスト 7割/問題集 3割
2年目:テキスト 2割/問題集 8割
問題集に集中できたのが良かったと思います。
勉強時間を確保するために大切なこと
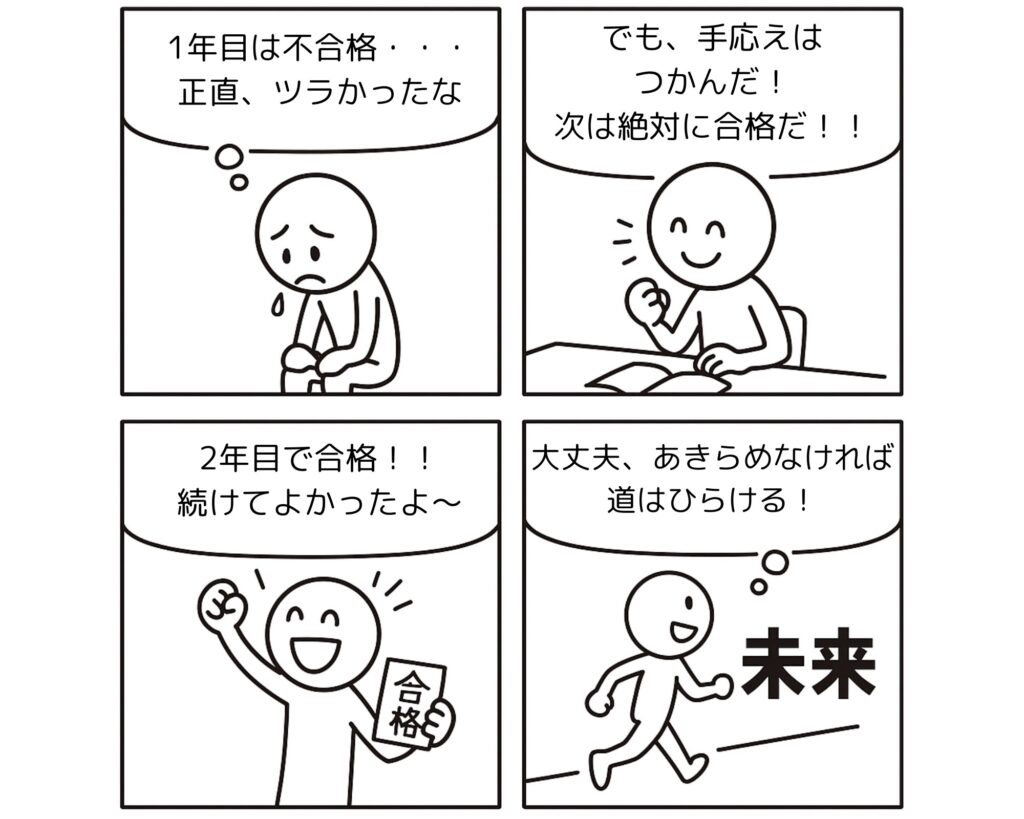
一級建築士試験に合格するためには、1,000~1,500時間の勉強が必要と言われています。
数字だけを見ると、「高すぎるハードルだな…」と感じる方も多いでしょう。
私も最初は同じ気持ちでした。
実際に合格した今、強く思うことがあります。
それが、合格につながる一番の近道だと実感しました。
私自身、最初から順調だったわけではありません。
途中参加、情報不足、やることの多さ、焦り、不安、迫りくる試験日……。
分からないことだらけで、思い通りに進まないことの連続でした。
それでも、「できることだけでも、やっておこう」と、少しずつ時間を積み重ねていきました。
結果、2年かかりましたが、無事に一級建築士試験に合格することができました。
仕事に育児、毎日忙しくて当たり前。
😰「今日もできなかった」
😥「もう間に合わないかも…」
それでも、たった10分だけやってみましょう。
その10分が、未来を変える第一歩になります。
一級建築士試験に挑戦するすべての社会人へ。
この体験記が、あなたの背中をほんの少しでも押せたなら、とてもうれしく思います。